「コラム」に
関する記事一覧
-
/
-

コラム#4-7 気仙沼から伝えられることって、何だろう。
気仙沼から伝えられることって、何だろう。 大学卒業直前の2月。ゆきちゃんは、能登半島地震で被災した子どもたちを支援するボランティアに行くことにした。 向かったのは、石川県羽咋市にある国立能登青少年交流の家。災害の現場復旧ではなく、子どもたちが被災地から離れて過ごすリフレッシュキャンプのサポートだ。 「東日本大震災の時に学生ボランティアが来ていて、それを見ていたので、大学生になったら自分もやりたいと思っていました。そんな時に、拓馬さんと能登の復興支援の話になって、ぜひ行きたい!って」 彼女は毎日子どもたちとのかかわりに奮闘した。その様子を毎日気仙沼の人たちにレポートとして送った。それを読ませてもらった時、能登の子どもたちに誠実に向き合うからこそ葛藤し、喜びも苦しさも、いろんな感情を抱えながら活動している様子が伝わってきた。 これからやりたいことを聞いてみると 「何度でも能登の現地に行きたい」と言う。 何度でも、か。その言葉を反芻していると、ゆきちゃんがこう答えた。 「自分がそうしてもらったからです。あの時、何度でも来てくれたから」 その姿を見ていたからこそできることがあるのだなと、彼女の話を聞いていて思う。「気仙沼から能登の人たちに伝えられることってなんだろうね」と聞いてみると、彼女は悩んでしばらく唸るように考え込んだ。 「うーん……。私が言えること、ないんですよね。何も言わないと思います。『一緒に頑張りましょう』もなんか違うし。うーん、難しいですね。何も言わないけど、ただその人たちと一緒に生活を送ると思います。ボランティアとしては、ただ一緒にいたいですね」 彼女はこの春大学を卒業し、まちづくりの研究を深めるべく大学院へ進んだ。これからも能登の復興支援に行く予定を立てている。 してもらってうれしかったこと、ありがたかったこと、かっこいいと思った大人の姿。次の世代へ受け継がれていくものは、今の私たちの生き方そのものにあるのだと、背筋を伸ばした。 (3/3) photo by asami iizuka ほかにも気仙沼の暮らしに関するコンテンツ発信中! Instagram「海と暮らせば」はこちらから
-

コラム#4-6 気仙沼から伝えられることって、何だろう。
気仙沼から伝えられることって、何だろう。 高校卒業後の進路は、大学でまちづくりを学ぶことに決めた。 ずっと東京に出たい気持ちもあったし、気仙沼で出会った大人で一番影響を受けた、まるオフィスのたくまさんが学んだ大学だったからだ。 たくまさんのどういうところに影響を受けているのか聞くと、「常に新しいところですね。変化しようとしているところ。一緒にいて面白いなって思います」とゆきちゃんは言う。 大学生になってからもたくまさんとのつながりは絶えず、探究学習の学生コーディネーターとして気仙沼に関わり続けた。 「気仙沼には大学がないから、ちょっと歳の離れたお兄さんお姉さんって、憧れがあったんです。自分が子どもの頃も、大学生が企画したワークキャンプとかに参加して会う機会があって、それで自分もやりたいって思ったんです。あの時はしてもらったから、自分がサポートする側に回ろうって」 元々地元を早く出たいと思って東京へ行った彼女は、今の気仙沼をどう思っているのだろう。 「大学にきて思うのは、帰ってこれる場所があるって良いなって。『ただいま、おかえり』って言ってくれる場所。周りから、ふるさとがあることを「良いな」って言われることが多いんですよ。あとは、面白い人が多いですね。自分の好きなこととかやりたいことを持っていて、自分の人生を生きている人」 東京と気仙沼。大学生活を過ごしながら気仙沼とも関わり続けて活動するのは、簡単ではないだろうなと想像する。それでもずっと気仙沼に関わり続けるのは、なぜだろう。 「声をかけてくれる人たちがいて、その人たちが面白いからです。やる時はちゃんとやるし、ふざける時は全力でふざけるし。そういう大人って良いなって思うし、一緒にいたい、関わっていたいって思います」 かつては、ここには何もないと思っていたゆきちゃん。だけど今、「面白い」と思う人たちは気仙沼にいて、いつも刺激をもらっているのだ。 (2/3) photo by asami iizuka ほかにも気仙沼の暮らしに関するコンテンツ発信中! Instagram「海と暮らせば」はこちらから
-

コラム#4-5 気仙沼から伝えられることって、何だろう。
気仙沼から伝えられることって、何だろう。 次に会いに行ったのは、気仙沼出身でこの春大学を卒業したゆきちゃん。 学業に励みながら、気仙沼に定期的に通って地元の高校生たちの探究学習をサポートするなど、高校を卒業してからも積極的に気仙沼と関わり続けている人だ。 「もともとは地元が嫌いだったんですよ。テレビ見てると東京のイルミネーションとか原宿の竹下通りとかが映って、それに憧れてました。ふと見たら、ここには何もないなって思って」 東日本大震災の時は小学3年生。当時、復興ボランティアとしてたくさんの人が気仙沼に関わり、「このまま気仙沼の復興を手伝いたい」と移住する人もいた。夕妃ちゃんは、移住者たちが企画するまち歩きのイベントに参加するようになった。 「移住者の人たちは、歩きながら分からないことが出てきたら、地元の人たちに『これはなんですか?』と聞いて面白がっていたんです。自分は都会に憧れていたし地元を早く出たいと思っていたから、『変なの』って思ってました。それから、『漁師さんってかっこいいよね〜!』と話す方もいて、衝撃的でした。父と祖父が漁師だったので、当たり前すぎて感覚が分からなくて。自分の方が長く住んでいるのに、移住してきた人たちの方がこのまちの良さを知っているのは、悔しさもありました」 いつのまにか、嫌いだった地元を「そういう見方もあるのか」と捉え方が変わっていった。それまでは学校と家を行き来するだけだったのに、週末は大人たちと会うようになり、それがとても楽しかった。 「『こういうイベントあるよ。来ない?』って声をかけてくれるんです。『この大人が言うなら絶対楽しいだろう!」って思って参加してました。楽しいことをやってくれる、ワクワクさせてくれる大人だなと思っていました」 高校生になると、これまた楽しそうな大人たちに誘われて探究型のプロジェクトに参加。探究することの面白さを知り、世界をどんどん広げて行った。 (1/3) photo by asami iizuka ほかにも気仙沼の暮らしに関するコンテンツ発信中! Instagram「海と暮らせば」はこちらから
-

コラム#4-3 気仙沼から伝えられることって、何だろう。
気仙沼から伝えられることって、何だろう。 「僕が力になりたいと思えば思うほど、気仙沼の人たちが考えていること、感覚に近づきたいって思って一生懸命頑張るわけですけど… 2016年の、3月11日のちょっと前だったと思うんですが、気仙沼のある方にお会いした時に、いつも明るくて元気な方なのに、すごくテンションが低かったんです。『3月11日に近づいてくると、気持ちが沈んでくるの』って。 ちょうど5年の節目。みんな頭の中で「5年後はこうありたい」ってビジョンを描いて、復興を目指してやってきた。そのビジョンと現実との、初めての答え合わせの日だったんですよね。 その時に、全く自分たちのビジョンに追いついていない現実を目の当たりにする。そこから次の5年後を描かなきゃいけない。そうなった時の虚無感というか、無力感みたいなものって、僕の心じゃちょっと追いつかないくらいのものだろうなって。本当に、力になれるのかなあ、と無力感を感じました」 それでも気仙沼に関わり続けてきたのは、なぜだったのか。 (2/3) photo by asami iizuka ほかにも気仙沼の暮らしに関するコンテンツ発信中! Instagram「海と暮らせば」はこちらから
-

コラム#4-2 気仙沼から伝えられることって、何だろう。
気仙沼から伝えられることって、何だろう。 浅草の仲見世通りにある、梅干しと定食の店「梅と星」@ume_to_hoshi へ。 鶴亀食堂がここでイベント的に気仙沼産のカツオやわかめ、メカジキを出したり、斉吉商店が海鮮丼を出したりしたこともあり、東京と気仙沼をつなぐ場所にもなっている。 この場所を運営するのは、株式会社バンブーカットの竹内順平さん。 「気仙沼漁師カレンダー」を気仙沼つばき会と一緒に制作してきた、気仙沼と切っても切れないご縁の方だ。 竹内さんが始めて気仙沼を訪れたのは、2012年にほぼ日が開催した「気仙沼さんま寄席」の時。当時は大学を卒業したてで、ほぼ日のアルバイト未満のような状態。お手伝いのような、付き添いのような、そんな形でスタートした。それから「気仙沼のほぼ日」ができて、通う理由ができた。 「何かと手を挙げて、力になれるなら、なんでもやります!って感じでした」 2年ほど働いたほぼ日を卒業してまもない頃、ご縁あって漁師カレンダーの制作に携わることになった。 「ほぼ日にいられたおかげで、微力ながらも力になれる環境にいられたんですけど、卒業したらなんの力にもなれなくて、関わり続ける仕事をつくることもできなくて。そんな中でいただいたお話しだったので、ご縁が切れなかったという喜びは、すごく大きかったですよ」 これまでとは違って、自分でプロジェクトを回していかなきゃいけない中で、どうしたら力になれるのかたくさん考えたという。そして今年、最終章となった10作目が完成した。 「本当に力になれたのか、今も答えはわからないです。でも、なってると思ってもらえたら良いなと思います」 答えはわからない。そう話す竹内さん。どんな思いで気仙沼に関わり続けてきたのだろう。 (1/3) photo by asami iizuka ほかにも気仙沼の暮らしに関するコンテンツ発信中! Instagram「海と暮らせば」はこちらから
-

コラム#4-1 気仙沼から伝えられることって、何だろう。
気仙沼から伝えられることって、何だろう。 2024年の1月1日、能登半島地震が起こった。 テレビからは、力強い声で情報を伝えるキャスターの声。 L字バーに津波の到達情報が映し出されている。 みんな逃げてほしい、助かってほしいと祈るしかなかった。 テレビ越しに感じる緊迫した状況の中で、ふとよぎったのは 「あの日、気仙沼もこんな風に見られていたのかな」ということ。 13年前のことを、自然と思い出していた。 この13年、いろんなことがあった。 まちは時間をかけて変化してきた。 そして本当にたくさんの人が、気仙沼に関わってくれた。 気仙沼でがんばる人も、 離れたけどずっと思いを寄せる人も、 あの日を機に気仙沼に関わり続ける人も。 一人ひとりに、13年間の軌跡と、思いがある。 東日本大震災を経験した気仙沼だから 伝えられることがあるんじゃないか。 大げさかもしれないけれど、きっとあるはず。 そう思って、3人の方に会いに行くことにした。 photo by asami iizuka ほかにも気仙沼の暮らしに関するコンテンツ発信中! Instagram「海と暮らせば」はこちらから
-

コラム#3-6 地球にも人にも優しい暮らしって?
地球にも人にも優しい暮らしって? 今あるものを見つめて大切にすること。 消費するだけでなく、創造的であること。 仲間と一緒にやってみること。 くるくる喫茶や勝手に環境庁の話を聞いていると、「地球にも人にも優しいって、実現できるのかも」と希望が湧く。 私はどこかで「一人とか少人数が動いたところで、現状は変わらないだろう」と勝手に諦めていたけれど、そうじゃないんだと思った。 一人ひとりのエコな選択と行動が増えたら、そこから変わるかもしれない。 そう信じられる今、私はとにかく実践するのみだ。 photo by asami iizuka ほかにも気仙沼の暮らしに関するコンテンツ発信中! Instagram「海と暮らせば」はこちらから
-

コラム#3-5 地球にも人にも優しい暮らしって?
地球にも人にも優しい暮らしって? 「気仙沼勝手に環境庁」( @kankyo_ksnm) やりたいから、「勝手に」環境に優しいことを学び、実践する仲間が集まっているコミュニティ。最初はあすかさんが旗を立て、活動していくうちに仲間が増えていき、今は20人以上のメンバーがいる。 私は、詳しいわけでも実践しているわけでもなかったけれど、環境に優しくなりたくてメンバーになった。まずは知ることから、参加することから始めようと思い、これまで開催されたイベントに参加してみた。 廃棄されるはずだった食材を集めて作った料理を振る舞う「もったいないキッチン」、古着屋、キエーロ作りワークショップなどを盛り込んだイベント「勝手に環境通り」。ギフト経済のトライイベントとしてお金ではなくみんなが持ち寄った食材をシェフが美味しく料理してみんなでいただく「もちよりキッチン」。エコバッグやタッパーを持ち込んで必要な分だけ欲しいものを買える「量り売りマルシェ」。コンポストの勉強会などなど。 参加するうちに、自然と「環境に優しいことってなんだろう?」と考える時間が増えたし、知らない間に自分の価値観がどんどんアップデートされていることに気づく。 私はまだ誰かの「勝手に」にのっかって楽しくやっているけれど 自分の「これやりたい」にみんなを巻き込めるようになりたい。 一人でできることには限界があると、仲間が増えて気づく。 みんなと一緒にやるから、楽しい。 写真提供 矢野明日香 ほかにも気仙沼の暮らしに関するコンテンツ発信中! Instagram「海と暮らせば」はこちらから
-

コラム#3-4 地球にも人にも優しい暮らしって?
地球にも人にも優しい暮らしって? 2016年に気仙沼に移住したあすかさん。 今は自分の畑で好きな野菜を育てたり、鶏と一緒に暮らしたりと、自然とともに生きる暮らしをしているけれど、もともとは東京のIT企業でエンジニアをしていた。 都会で働く中で、ものすごいスピードで進む物事に違和感を覚えたり、体調を崩した時に、食べることが命につながっていることを実感したり。 その経験から、自分が食べるものを自分でつくる暮らしを、気仙沼の唐桑という自然豊かなエリアで始めた。 あすかさんは「畑のsoup屋さん」 @hatakenosoupya の顔も持っている。友だちと一緒に始めた畑で育てた野菜を、みんなに気軽に味わってもらえたらと、イベントに出店している。 「もっと上手に自然と暮らすことを学びたい。私もわくわくするし、自然にとっても良い、そんな風に暮らしのなかに循環が生まれたら」 その思いを種にあすかさんが2020年に始めたのが「気仙沼勝手に環境庁」。 @kankyo_ksnm 「くらしから みらいをかえる」をテーマに、環境にやさしい暮らしを学び、実践する人たちの集い。今実践している人も、これからそうなりたい人も仲間になって、みんなで取り組んでいる。 「勝手に」というのがミソ。強制でもなく、義務でもない。 みんな勝手にやって、それが集まるから楽しくなってくるのだ。 写真提供 矢野明日香 ほかにも気仙沼の暮らしに関するコンテンツ発信中! Instagram「海と暮らせば」はこちらから
-

コラム#3-3 地球にも人にも優しい暮らしって?
地球にも人にも優しい暮らしって? くるくる喫茶の向かいに、もともと酒屋さんだった建物がある。窓ガラスには「お直し考」と書かれている。2023年3月、この場所で開催されたイベントに参加した時に初めて知った言葉だった。 例えば靴下に穴が空いてしまった時、捨ててしまうのではなく自分の好きな色の糸で縫って穴を塞ぎ、お直しして靴下の寿命を伸ばす。 例えば自分が使わなくなった食器や本、子育てグッズなどを蚤の市などに出して今必要とする人に提供する。 いらなくなったら捨てて新しいものを買うのが当たり前になっているけれど、その「いらないもの」は誰かにとっては価値のあるものかもしれないし、ひと工夫で新しい使い方ができるかもしれない。 今あるものの価値を見つめてみる。消費ではなく、創造する。手間をかけるから、愛着が湧く。そしてまた誰かがその価値を見つめて、活かす。その循環を生むのが「お直し考」だと、私は受け取った。 イベントが終わった後、ここもくるくるの棚になった。窓際には誰かが持ち込んだ食器や小物が並んでいる。良い出会いがあれば、誰でも持って行って良い。 並んだ食器たちの中で、一つの灰皿が目に止まる。昔の飲み屋さんで使われていたであろう青いプラスチックの灰皿。レトロなロゴが可愛らしくて、持ち帰ることにした。今、部屋でアクセサリートレーとして使っている。 ものを大切にするための、価値のバトンパス。 これが広がったらいいなと、日に照らされた食器たちを眺めながら思った。 (前の投稿にもあるように、自由気ままに新しいことを楽しむお店なので、訪れた時にはまた新しいことが起こっているかも。それは今後のお楽しみ。) photo by asami iizuka ほかにも気仙沼の暮らしに関するコンテンツ発信中! Instagram「海と暮らせば」はこちらから
-

コラム#3-2 地球にも人にも優しい暮らしって?
地球にも人にも優しい暮らしって? 気仙沼の八日町のまちかどにある「くるくる喫茶」。 @kuru2utsumi 木製の看板には「コーヒー、wi-fi、軽食、電源、その他」の文字。仕事をしたりゆっくりコーヒーを飲んだり、おしゃべりしたりできる喫茶店だ。若い移住者から地元のおじいちゃんおばあちゃんまで、いろんな人がここに集まる。みんなから親しみを込めて「くる喫(きつ)」と呼ばれている。 気仙沼の老舗菓子店だった建物を、店主の吉川晃司さんがリノベーションしてこのお店をつくった。ちなみに名前の読み方は「よしかわ」さんだ。初めて会った人によく「えっ、あの人と同じ名前?」とつっこまれるらしい。 くる喫ではよくイベントが開催されていて、空間の表情がくるくると変わる。 インドネシアから気仙沼に来て働いている技能実習生たちと繋がる1日カフェをやったり、アート展示の会期を設けたり、弾き語りライブをしたり。吉川さんが好きなもの・こと・ひとを介して多様な人が集い、それぞれ自分の「好き」を楽しむ場所になっている。 そんな空間に2022年の冬に現れたのが「くるくるの棚」。 置かれているのは食器や花器、本や小物など。地域の人たちがいらなくなったものを持ち寄ったものだ。これらは、一筆書けば全て持っていって良いものだという。 誰かがいらなくなったものが、誰かにとっての欲しいものになる。 誰かから誰かへ渡る価値の循環がこの棚から生まれている。 毎日ものすごいスピードで大量の新しいモノが生産され消費されているけれど、「あるもの」の価値を信じる人が増えたら、 世界は地球にも人にも優しく変われるんじゃないか、と思う。 (ちなみに、自由気ままに新しいことを楽しむお店なので、訪れた時には空間が変化しているかもしれない!それもお楽しみに) photo by asami iizuka ほかにも気仙沼の暮らしに関するコンテンツ発信中! Instagram「海と暮らせば」はこちらから
-
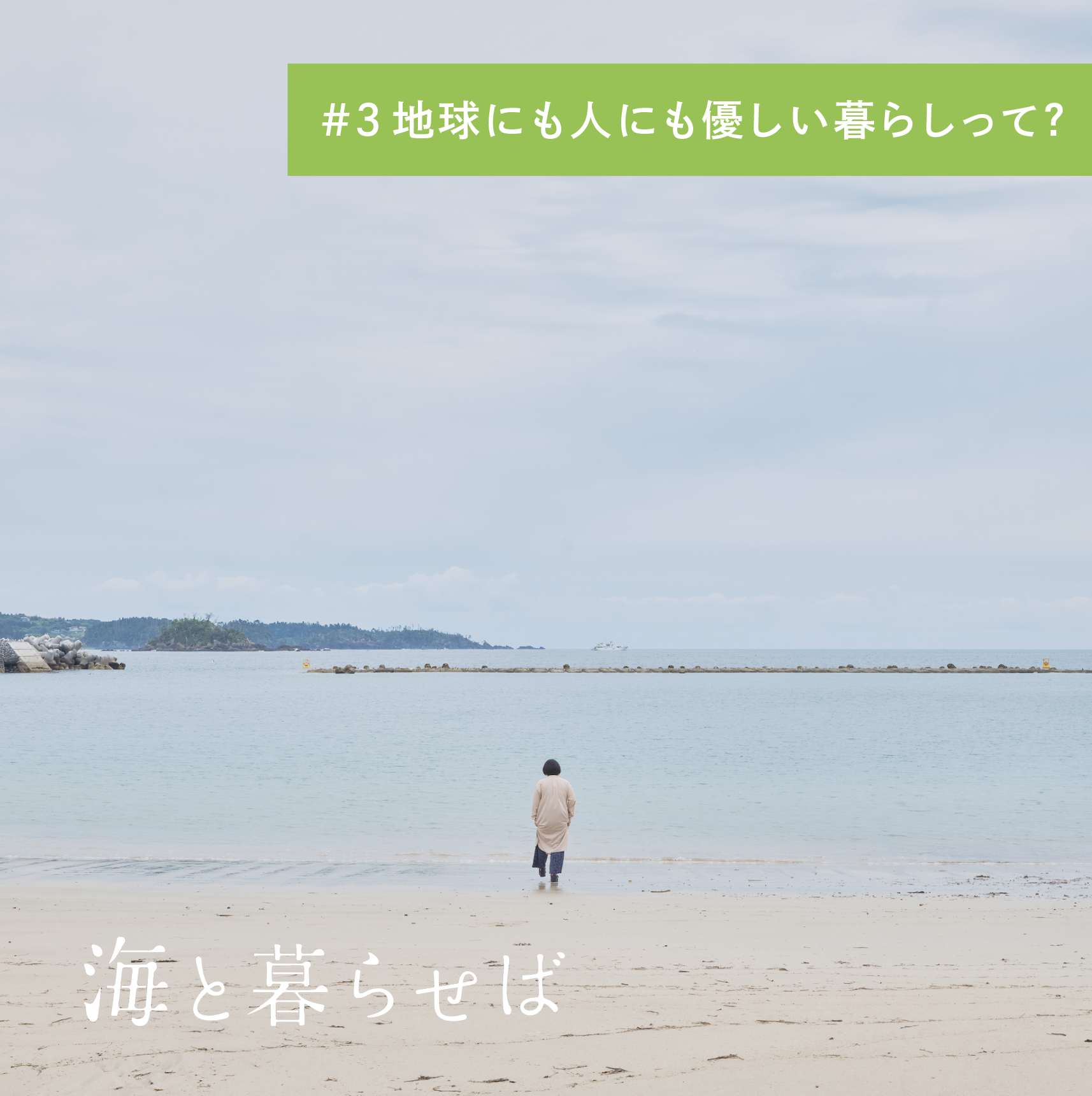
コラム#3-1 地球にも人にも優しい暮らしって?
地球にも人にも優しい暮らしって? 「持続可能」とはよく聞く言葉だけれど、なんだか壮大で、考えるのをやめてしまう自分がいた。 自然環境に優しいことをしたいし、 人間以外の生き物にも健やかであってほしい。 そんな思いを持ちながら、忙しない日々に流されていく自分。 正直、目の前のことで精いっぱいだ。 でも、このまま「あ〜何にも地球に良いことできてない」と思い続けるのはごめんだ。 できるだけ楽しく、地球に良いことをしたい。 楽しい方が、続けられる気がするから。 じゃあ私にできることって、何だろう? マイボトルやエコバッグを持ったり、 ゴミ拾いをしてみたり、移動手段を公共交通機関にしたり。 自分なりにやってみているけれど、 もっとできることはないだろうか。 そのヒントをもらいに、気仙沼にいる人たちに 話を聞いてみることにした。 photo by asami iizuka ほかにも気仙沼の暮らしに関するコンテンツ発信中! Instagram「海と暮らせば」はこちらから

